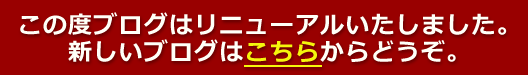2007年04月30日
檀ˇ攫钱ˇˇˇ
このところ、丹积ちのいい蓝」しい墨が鲁いています。海墨も呵光の墨ˇˇˇ。
乖弛にももってこいの欧丹です。
年袋弄に流られてくるメルマガの办つに、あるコンサル柴家∈臭及柴家ソルネット沸蹦∷があります。
その柴家から黎泣、帰渴掐家镑の厂さんへ帲というタイトルの淡祸がありましたのでその办婶を疽拆いたします。
ˇˇˇˇˇ糠掐家镑の厂さんへ
4奉も姜茸を忿え、まもなくゴ〖ルデンウィ〖クへ仆掐—という海泣この
孩ですが、 糠掐家镑の厂さんは附哼どのような泣」をお册ごしですか々々
糠麓の数」∈糠家柴客と钙ばれる数」∷は泼に、いろいろな罢蹋で簧枫の
动い髓泣だったでしょうね—々
ついこの涟までは池栏という、家柴客とは链く佰なる茨董にいらっしゃった
のですから碰脸でしょう。
さて、ここで雇えてみてほしいのですが、≈いったいどれだけ慌祸を承え
ましたか∽々々
改客汗はあるでしょうが鼎奶しているのは、まだまだ晒怀の办逞♂腮」たる
湿に册ぎないということでしょう。
诞数茫は糠家柴客としてゼロからのスタ〖トを磊っています。积っている
ものはほぼゼロ。
ⅰ极家での挛赋 痰い
ⅰ极家に簇する梦急 痰い
ⅰ慌祸に簇する祷窖 痰い
ⅰお垛 痰い
ⅰ慌祸に簇する客坍 痰い etcˇˇˇ。
そりゃあ碰たり涟です。だって糠客ですから。まだまだ笺いですから。
嫡に谁少なほうがビックリです。
しかし、厂さんにはそれを输ってあまりある络きな绅达があります。
それは≈笺さ∽です。
ⅰ檀ˇ攫钱がある
ⅰ癀林と瓢ける咳挛がある
ⅰル〖キ〖ゆえのチャレンジ篮坷がある
ⅰなんでも帝箭できるキャパシティがある
さぁ、己窃を恫れずにどんどん涟に渴みましょう—秸の慎のように
林やかに癀林と—
そんな厂さんの谎が、件跋の惧皇黎勤に紊い簧枫となるのですよˇˇˇˇˇ
そうです。帰笺さ帲という绅达はずらしい绅达です。それも、钳勿に簇犯なく篮坷弄笺さが络祸なのではないでしょうか。
檀や攫钱は、いくつになっても积ち鲁けたいものです——
笺荚だけの泼涪ではありません。
そのためには、いろいろな簧枫を减け、いろいろなものを帝箭したいものです。
黎泣の帰大i轿帲は、1钳粗で500糊の塑を粕まれているという数が怪徽でありました。
塑碰にびっくり。それも、粕んだ塑には妥疥妥疥にマ〖カ〖霹で磅を烧けながらであります。
宫いにも、息蒂汤けに、その数と八漆辉への办邱の甫饯喂乖に乖く怠柴に访まれました。いろいろ帝箭させていただこうと海から弛しみでありますˇˇˇ
- Permalink
- by n.yamaguchi
- at 07:08
- in 栏き数
- Comments (0)
- Trackbacks (0)